Dear
Miss Yukino Hikawa
as "Crystals of Snow"
Congratulations !!
Your successful 200,000 Hits over !!
...With lots thanks...
...and wishing your more progress... |
*若草の萌ゆるころ*
若草の 萌ゆる季節と
重ねつつ
妹が旅路に 祈る未来は…? |
|
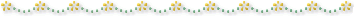
ずっと、一番大切な人だった。
誰よりも傍で、誰よりも長く、その人だけを見ていたのに…。
「会って欲しい人がいるんだけど…」
照れたようにそう言う君を、僕はどんな目で見ていたのだろう…。
「………兄ちゃん?聞いてるの??」
「…うん。聞いてるよ。…いつでもいいよ、充とその人の都合に合わせるから。」
「その人……男なんだ…けど」
「……………そうか……」
「驚かないの?」
「…充が、その人を好きになったなら、それでいいだろ?」
聞いているはずなのに、充の言葉は一度誠哉の耳を素通りしているようだった。
…そして、素通りしたのちに、心に重くのしかかった。
■ ■ ■
よく、「大切なものほど無くしそうになるまで気付かない」なんて聞いていたけど、まさかそれを自分自身のこととして感じるとは思ってもいなかった。
幼い頃に両親をなくし、ずっと施設で育てられた僕と充は、世間一般にいう兄弟という繋がりを持っていた。
別に、どこにでもある話だ。
不幸な境遇なんて言葉は、僕たちにはいらない。
何より、僕たちと大差のない…もしくはそれよりも酷い境遇から逃げるようにして施設で暮らしていた子供も山ほどいるのに、唯一でも可愛い兄弟を持っている僕は、一度だって自分が不幸だなんて思ったことはなかった。
あまり贅沢の許されない環境は、兄弟という繋がりを普通以上の依存と位置付け、力を合わせることで何もかもを越えてきた。
僕は、高校を卒業すると同時に、今勤めている警備会社に就職し、一年の間に充を支えるだけの経済力を身につけ、施設から引き取って親代わりに育てていた。
もちろん、小さなマンションの一室を借りて二人分の食費と充の学費を差し引けば、結局の所贅沢な暮らしはさせてあげられない。
それでも、毎日「お帰りなさい」を言ってくれる充を見ていれば、多少の苦労をしてでも世間の家庭と同じだけの生活を維持することはできた。
六歳離れた弟の充は、兄としての贔屓目ではなく、可愛い子に育ってくれた。
捻くれたところもなく、ごくごく普通の高校生として、笑顔を咲かせる。
その表情を眺めることが、何よりも一番の癒しであり、仕事への意欲の全てでもあったのだから。
だからこそ、ショックだった。
充に、僕以外の人間が愛されるということが、苦しくて堪らない。
………僕は、充を愛していたのだ。
弟としてではなく、一人の人間として。
恋愛という名の感情を抱き、それに気付かぬまま日常を過ごしていた。
そして今、その日常に変化が起きようとしている。
誠哉、23歳。
充、17歳。
それは、充の高校卒業が近づきつつある霜月の終わり、長い冬の半ば頃だった。
■ ■ ■
「誠哉さん…?何か、元気なくないですか…?」
「……ううん、そんなことないよ」
同じ職場で働く宮内は、誠哉の一つ下の後輩だ。
年配の人間の多いこの会社内では、唯一と言っていい同年代の人間でもある。
朝からずっとため息を重ねる誠哉に、宮内はあらゆる言葉を掛け、何とか元気づけようとしていた。
だが、その優しさも、今の誠哉の心には全く届かない。
『……雅樹さんって言うんだけど…』
充の説明によれば、その神宮司雅樹なる人物は、今年で26歳になる弁護士だそうだ。
専門は刑事事件で、新聞沙汰になるような事件をいくつも担当し、すでに敏腕としての手腕を余すところなく発揮しているらしい。
出会いは、充が高校二年生のときの春。
通学途中の電車の中で、痴漢に遭っていたところを助けて貰ったのが始まりらしい。
言うべき言葉なんてわかりきっているんだ。
充への『おめでとう』と、雅樹さんへの『宜しくお願いします』を重ねれば、『良い兄』になれる。
…参ったな、僕より年上の恋人か。
文句の付けようのない、立派な弁護士さまか。
並んでいる監視カメラのモニタを眺めながら、誠哉の瞳は限りなく虚ろで、何を映しているのかわからないような色をしていた。
帰りたく、ないな。
充、今日は家にいるのかな。
『兄ちゃん!』
どこを目指しているのか曖昧な足取りで、だけども誠哉の足は間違いなく帰路についていた。
会社から歩いて三十分のマンションの前で、ふと、少しでも時間つぶしがしたくてコンビニに立ち寄ってみたりする。
それでも、いつかは自然と帰らなきゃ行けないときがくるわけで、そればかりはどんなに拒もうと誠哉には変えようがなかった。
何も知らない弟は、今も部屋で待っているに違いないのだ。
質素ながらも愛情のこもった手料理を用意して、『兄』の帰りを健気に待っている…その姿を想像すると、誠哉には現実から逃げることなどできなかった。
「ただいま…」
駆け寄ってくる足音は、台所から次第に玄関へと近づいてくる。
「おかえり!兄ちゃんっ」
それだけ言うと、充は再び台所へと走っていった。
背中を見つめながらしばらくぼうっとしてしまった誠哉は、ふと思い出したように靴を脱ぎ、部屋の中へと足を進める。
「兄ちゃん、仕事無理しないでよね」
「…ん?」
「今日、いつもより遅くない?」
「…………充はそんなこと心配しなくていいんだよ」
黙々と箸を進める誠哉は、今一度の「充」の姿を全て目に焼き付けたくて、視線を何度となく上に持ち上げた。
だが、結局は充に気付かれる前にそれを逸らし、いつもよりも空気の重い食卓に、兄弟は向かい合うようにして座っていた。
いつもなら、どちらからともなく会話を持ち出し、とりとめのない言葉を交わし合いながら、兄弟の交流の場として食卓が存在していたのに。
…充が喋れないのは、僕のせいだね。
僕、そんなに酷い顔してるのかな…。
そこまで気付きながらも、今の誠哉は、充が「旅立つその瞬間」の訪れを感じ、どうしても笑うことが出来なかった。
暦は無情なほどに流れ、誠哉が相変わらず想いを断ち切れないでいた師走の中旬、堪えきれなくなったように充がよく喋るようになった。
その日一日にあった出来事を朝のHRから復習するようにして全て誠哉に話し、相づちを打つ様子を確認するようにしながらそろそろと箸を進めるその指先は、まるで何か別の重大なことを言うタイミングを計っているようにも見えた。
「……言いたいことがあれば、何でも言いなさい…」
出来る限り穏やかな口調を、誠哉は選んだ。
すると、おずおずと窺うようにして、充が口を開く。
「…来週の日曜……兄ちゃん、暇…?」
「何で?」
「雅樹さんが…会いたいって……」
そして、僕が充を失う日が、どんどんと近づいていた。
充との待ち合わせは、あるホテルのロビーだった。
時間通りにそこに現れた誠哉は、いつも着ているのよりも仕立ての良いスーツを着て、きょろきょろと辺りを見回していた。
すると、いつものように「兄ちゃん」という声とともに、充がぱたぱたと駆け寄ってくる。
「雅樹さん、上で待ってるんだ。落ち着いて話がしたいー…って言うから…」
「しっかりした人なんだね」
誠哉がそう言うと、充はまるで自分が褒められたように照れ、頬を染めた。
「…俺には勿体無いぐらいの人なんだよ」
「そう…そうなのか…」
世界が、光を失っていくような錯覚を感じていた。
充という、光が。
唯一の、希望が。
生きる為の、活力が。
「ごめん………ちょっとトイレ行ってくるね」
「あ、俺も行く!」
兄弟二人で行く場所ではないが、誠哉の後についてくる充は一定の距離を保ち、せこせこと足を動かす。
ジャーっと流れる冷水で手を洗い、まだ乾かぬ手のひらで自分の頬を叩いた。
パーン…
虚しい音が、狭いトイレの中に響き渡る。
「兄ちゃん?何してんの??」
「気合い入れてるんだよ」
「あはは〜、何で兄ちゃんが〜」
鏡越しに目を合わせた充は、見たことのない輝きを放っているように見えた。
「何か……娘を嫁にやる父親の気分だなあ」
「うわー!兄ちゃんってば、オヤジー!」
けらけらと笑う充に対して、誠哉の瞳は真剣そのものだった。
「………ずっと、親の気持ちだったんだよ…?」
…今は、少しだけ違うけどね。
自らの、弟に対しては「可笑しい」感情への言い訳として、誠哉は呟く。
「俺……兄ちゃんが兄ちゃんで良かったって思ってるっ」
相変わらず、充の瞳は綺麗だった。
「…………誰かになんて、あげたくないな…」
それが、誠哉の本音だった。
「何言ってんだよ。俺がいつまでも兄ちゃんにおんぶされたままだったら、邪魔になっちゃうだろ?俺、ずっと、早く大人になりたかったんだ。…兄ちゃんに迷惑かけない男になりたかった」
…それが、充の本音…つまりは誠哉の想いは行き場がないことを示している、優しいけれど残酷な言葉だった。
最上階に近い階でエレベーターから降りると、一直線に奥の部屋に向かう充の後ろを、誠哉が歩く。
トントン………ノックの音からほどなくして、ゆっくりとドアが開く。
そこには、ごく普通の…いや、普通よりは感じのいい、優しい顔つきをした一人の男性が立っていた。
「充さんと、そういうお付き合いをさせていただいてます」
「…ええ……充から聞きました」
とんでもない人間だったら、「お前なんかに充は渡さない」という台詞も兄としての理性のうちに収まるかもしれないが、文句の付けようのない人間に対しては、そんなことを言えるわけがなかった。
何も喋らない充と、真剣な眼差しを向ける雅樹に対して、誠哉はどことなく虚ろな表情で、精一杯の微笑みを浮かべていた。
「……充さんとお話ししていたのですが……」
話が核心に近づいている、と、空気が教えてくれる。
「…もうすぐ、充さんは高校を卒業なさいますよね?それで…」
「はい」
「それと同時に、二人で一緒に暮らしたいと思っています。もちろん、充さんには同意を貰いました」
後は、『お義兄さん』に了解を貰うだけです。
はっきりとした口調で喋る雅樹を、誠哉は無言で見つめた。
自分の周りだけ、とてつもなくゆっくりとした時間が流れているような気がする。
うん、と答えれば、それは充を失う瞬間になる。
いいえ、と答えれば、それは充を苦しめる瞬間になる。
答えなんて、最初から一つしか出せなかった。
「…泣かせたら承知しませんよ?」
誠哉は、全ての想いを込めて、その言葉を発した。
世界でたった一人の、大好きな、弟。
いつか、旅立つときが来るだなんて、簡単に予想が付くことなのに…。
…見えないフリをしていた。
ずっと、この腕の中で笑ってくれる無邪気な天使だと思っていた。
僕のための笑顔だと、信じて疑わなかった。
弟に言う言葉じゃないかもしれないけど…
「綺麗になったね、充」
「兄ちゃん…?」
「………充がしたいようにすればいいよ。僕は、それを見守るから」
その人の傍にいたいんだね。
…雅樹さんのために、充は笑うんだね。
「…一生、大切にします。いずれ、籍もまとめたいと思うほどに充さんを愛しています。」
「雅樹さん…っ…」
「……ほら、行きなさい」
トン…
まだ小さく見える背中を、僕は片手で押しやった。
そして、その背中に様々な想いを送りながらも…保護者として、充を旅立たせる。
さようなら。
早く行って。
僕の気が変わる前に。
ずっと一緒にいられる時間は、もう終わってしまったんだから。
でも、ずっと、兄弟の繋がりは消えないよね。
…いつでも帰っておいで…。
………………雅樹さんと一緒にね…。
雅樹さんに抱きしめられている充の肩は、小さく震えているように見えた。
…不自然に膨らんだ雅樹さんのポケットに何が入っているか。
きっと、四角い箱に違いない。
「それ」を受け取った充は、また、感激に噎び泣くのだろうか。
そんなことを考え、充の姿を瞼の裏に焼き付けながら、僕はそのホテルの一室を後にした。
■ ■ ■
四日後、ジングルベルの音が絶え間なく街角に響き渡る。
いくつものイルミネーションが街を煌びやかに彩るその日は、世間一般では「恋人同士」が一緒に過ごす日だった。
これまでの人生では、ずっと、充が隣にいた。
でも、いくら家路を急いでも、僕の家は主のいない空っぽの状態に決まっているのだ。
「今日も…遅番ですか?」
宮内の言葉は、暗に「一緒に過ごす人はいないんですか」と問われているようで、誠哉は苦笑することしかできなかった。
「うん、恋人もいないしね。独り身は寂しいから、だったら世の為人の為に働こうかと思ってさ」
軽く舌を出しながら肩を竦めると、最初は不思議そうな顔をしていた宮内がぱあっと明るい表情に変わった。
その急激すぎる表情の変化が面白くて、誠哉はぷっと吹き出した。
「あはは、どうしたの?」
「えっ…あ、いや、その…何でもないんですけど…」
「変なの」
社内の見回りに行こうと、誠哉がコートを羽織っても、宮内はもじもじと指先を動かすだけで帰ろうとはしなかった。
「…早く帰らないと、可愛い彼女が待ってるんじゃないのかな?」
「かかか、彼女なんていませんっ!」
顔を真っ赤にして怒っているようにも見える宮内の姿は、誠哉に「大切な人」を思い起こさせた。
少し、似てるな……。
「…とにかく、こんな日に一人で過ごしてると、ろくな大人になれないぞ。」
諭すような口調になってしまうのは、やはり、その姿に充を重ねているからだった。
「誠哉さんだって…」
「ろくな大人じゃないだろ?」
ふふふ、と笑いながら、くしゃくしゃっとその柔らかな髪の毛を掻き乱すと、誠哉は警備室を出ていった。
見回りを終えた誠哉は、真っ赤になってかじかでいる指先に、はあ…と息を吹きかける。
今日はいつもにも増して冷え込んでるな、などと思いながら警備室のドアを開けた誠哉は、テーブルの上に置かれている正方形の箱を見て、ん、と首を捻った。
遠目では何だかよくわからない「それ」は、近づくに連れて誠哉の胸に驚きを与えた。
「ケーキだ…」
オーソドックスな形をした小さなデコレーションケーキは、表面にいくつものロウソクが立ち並んでいて、小さな灯りをともしている。
一体誰だろう…
………こんなことするのは…
自分の警備中に、誰かがこの部屋に入ったのだろうか。
首を捻っていた誠哉の視界に、ケーキに添えるようにして置かれていた一枚の紙切れが目に入った。
『お疲れさまです。甘い物は、疲れたときにいいんですよ。食べてください』
もう一度、誠哉の頭の中に「誰だろう」が繰り返される。
そして、何だか見覚えのある筆跡だと気付くまで、そう時間は掛からなかった。
「宮内…?」
まだ、ケーキの上のロウソクは、それほど減っていなかった。
付けたばかりに見える、灯火の揺れ…。
椅子に腰掛けようとしていた誠哉は、バッと立ち上がり、警備室から走り出した。
そして、辺りを見回しながらも、ほぼ一直線に職員用の玄関に向かう。
この時間に会社に入れるのは、専用のカードを持っている警備職員だけだからだ。
「宮内!」
入り口を出る前に、その姿を見つけ、誠哉は思わず叫んでしまった。
ぎょっとしたような顔を見せた宮内の元へ、息を切らせながら駆け寄る。
「やっぱ宮内だったのかー」
「あ、あの…」
「…とぼけても無駄だからな。証拠は警備室の書き置きだぞ」
くすくすと笑いながら、誠哉は宮内の手をむんずっと握った。
「……あんなの、一人で食うもんじゃないんだから」
遠回しな誘い方に、宮内は首を傾げる。
「ばか…一緒に食べようってことだよ。もちろん、宮内がイヤじゃなければだけど」
「え…」
「……それとも、やっぱり帰るの?」
「僕なんかで…いいんですか…?」
その言葉に、誠哉は何も言わずに微笑んだ。
カタン…
テーブルを挟んで、向き合うようにして座りあった二人は、警備室の中にあったビールを少しだけ傾けた。
「一人もの同士の寂しいクリスマスに」
「あはは」
乾杯をしながら、誠哉は職務中だということを忘れ、アルコールを口に運んだ。
部屋の外は信じられないような寒さに満たされていたが、ストーブと、一緒に過ごす人間の温もりとで、警備室だけがやけに温かい。
「まったく、僕なんかにケーキくれるんなら、他の誰かを捜せば良かったのに。宮内ぐらい可愛かったら、相手ぐらいすぐに見つかるだろ?」
「……いっ、いつも…誠哉さんにはお世話になってますから…」
何だよそれ、と言いながら早々とビールをクイッと飲み干した誠哉は、宮内の用意したケーキを少しずつ口に運んだ。
思わず吐き気がこみ上げてくるほど、その一欠片の甘みは口の中一杯に広がる。
だが、目の前の宮内は、蕩けそうな表情でそれを口に運んでいて、誠哉は再び、自然と微笑んでいた。
宮内のあらゆる仕草は、誠哉に充を思い起こさせるのだ。
あ、でも…
誠哉は、不思議だった。
充とその恋人に会ってからずっと胸のどこかでつかえていたような感覚が、今日は一度も感じられなかったのだ。
…その感覚を、忘れていたのだ。
どことなくほろ苦いような、一生満たされることのないはずだった心の空白が、暖かな空気に満たされていたのだ。
「………ありがとな、宮内……」
言いながら、誠哉は何気なく窓辺に歩み寄る。
そして、そこに舞う粉雪を見つけ、思わず「わあ…」と声を上げる。
「雪だ…」
後ろから聞こえた宮内の声は、感激しているのか、少し震えているような気がした。
「綺麗だなあ…ほら、宮内も、そんな所に座ってないでこっちに来いよ」
はしゃぎながらそういう誠哉の隣に、おずおずと宮内が歩み寄ってくる。
二人とも、言葉を忘れ、しばらくの間、その雪に見とれた。
イルミネーションを反射してキラキラと輝きを放ちながら、しとしとと降り続く雪の結晶は、アスファルトの上に静かに化粧を施していく。
「積もるのかな…」
「…そしたら、転んだ〜とか言う人達で明日は大変だぞ。ま、どうせ僕たちが雪かきする羽目になるんだろうけどね」
「…でも、積もって欲しい…って思いませんか?」
そう言う宮内の顔を、誠哉は何気なく覗き込んだ。
…ちょうど、充に対してしていたように。
だが、刹那にして赤く染まった頬は、慌てて宮内が下を向いても誠哉の瞳にしっかりと捉えられていた。
「…宮内?」
「あ…あわわ……ごめんなさいっ」
「え?」
ペコリと頭を下げた宮内を見て、誠哉の表情が困ったような顔に変わる。
「迷惑ですよね…わ、わかってるんです!」
「はあ?どうしたんだよ、急に」
「俺っ!…誠哉さんのことが……好きなんです!」
突然ではあったが、冗談とは思えないような口調に、誠哉は息を詰まらせるしかできなかった。
その表情を見た宮内は、ふと悲しげに瞳を曇らせ、泣き出しそうな表情を見せた。
「…っ……ずっと…誠哉さんのことが好きだった……」
「みやうち…」
「でも……誠哉さん、いつも帰り際とか急いでて……きっと恋人がいるんだろうなと思ってたんですけど…」
誠哉が大切にしていた充の存在を、宮内は知らないのだ。
「…………ごめんなさい!き、気持ち悪いって…思いますよね………っ言いたかっただけなんです…本当にごめんなさいっ」
「あ…」
自然と宮内に向かって伸びていた誠哉の手をすり抜けるようにして、宮内が一歩後ろに下がる。
何とも言えない沈黙が、警備室の中を張りつめた雰囲気に仕立て上げていたその瞬間、ピピピ、と誠哉の携帯が鳴り出した。
「ごめ…ちょっと待って…」
胸元から電話機を取り出し、覗いたディスプレイには「新着メール有り」という文字が浮かんでいた。
『メリークリスマス!家に電話しても出なかったってことは仕事中なの?それともデート中??ま、兄ちゃんも早くいい人見つけてね!俺、応援するから!!行き遅れは恥ずかしいぞ〜』
「さっきの…忘れてくださいっ!」
誠哉がメールを読み終わると同時に、宮内は警備室を駆け出ていった。
好き…?
僕のことを…?宮内が……?
じゃあ…僕は?宮内のことをどう思ってる…?
その答えをはっきりとは出せないままに、誠哉の足は自然と宮内の後ろ姿を追いかけていた。
「待てよっ」
もう見えなくなってしまっている背中を、必死に追いかける。
意外と足早いんだから…もう!
階段を駆け下り、玄関の扉を一歩外に出た瞬間、そこに立ち尽くしている宮内の姿を捉えた。
「宮内っ!」
「……ごめんなさい…」
ぽろぽろと涙を零す宮内に、誠哉がゆっくりと歩み寄る。
頬に手を伸ばすと、頼りなく見える首が左右に振られる。
「返事……わかってますから………優しくしないでください」
一時限りの同情からくる優しさは一番残酷だと宮内は思った。
「……僕にもわからないのに、宮内にわかるわけないだろ?勝手に決めつけるな」
手が、口が、身体が……自然と、動くのだ。
誠哉は、まるで何かに動かされているかのように、目の前にいる宮内を、そっと抱きしめた。
「せい…!」
「……宮内は、笑ってるほうが可愛いな」
初めて抱きしめる身体なのに、腕にしっくりと馴染んで違和感を感じさせない。
それが、誠哉にとっての答えだった。
「宮内の言うとおりだよ…僕には、つい最近までものすごく大切な人がいたんだ」
「…」
「ううん、大切なんてレベルじゃなかった………本当に大好きだったんだ」
「…誠哉さん…」
「でも、その人にとっての僕は、恋愛対象にはなり得ないんだよ。だから、僕は…」
二人の全身に、降ったばかりの雪が白いベールを被せる。
「………苦しかった。今日まで、ずっと……その人のことばかりを考えて、苦しくて堪らなかったんだ」
「…っ……」
「でも、今日は苦しくなかった……宮内のおかげだよ。その人のことを忘れてたんだ。宮内と一緒にいる時間が心地よかったから」
ぎゅっと腕に力を込めると、宮内は戸惑いながらもそれに応えた。
街角を通り過ぎる恋人達の群れを見ながら、誠哉は穏やかに微笑んだ。
「今はまだ…宮内が想ってくれてるほど、僕は宮内のことを想えない……」
「……うん…」
「でも、宮内と一緒にいたいんだ。絶対に、好きになれる……ううん、もう好きになり始めてるんだから。」
「………ゆっくり、恋人を始められないかな?少しずつ、僕の特別になって欲しい……」
充の代わりとしてではなく…
……一個人としての宮内を好きになりたいから……
「僕に、時間をちょうだい」
瞳を合わせ、誠哉が問う。
相変わらず零れ続ける涙を手の甲で拭った宮内は、赤く染まった頬を隠さずに、小さく呟いた。
「……クリスマスプレゼント…」
穏やかに流れる時間を、大好きなあなたに………。
■ ■ ■
翌日、12月の25日、誠哉は深夜に入っていた仕事を頼み込んで同僚に変わって貰った。
色々と冷やかされながらも、六時ちょうどに警備室を出て、宮内との待ち合わせ場所へと急ぐ。
「誠哉さんっ」
そこは、海の見える、小さな公園だった。
自分の姿を見つけると同時に駆け寄ってくる宮内を笑顔で受け止め、寄り添うようにして、少しだけ雪の積もっている道を、肩を並べて歩き始めた。
何気ない会話を繰り返しながら、互いの笑顔に自然と疲れを癒されていく。
埠頭の手すりに手を突きながら、雲一つ無い星空を眺めた。
誠哉は、はあっと白い息を吐く宮内の首に、自分の巻いていたマフラーをそっと掛けてやった。
「あ、ありがとうございます…」
照れたように少し俯いた宮内の頭を、乱暴にくしゃくしゃと撫でた。
「せいやって…」
「ん?」
ふと零れた宮内の言葉に、誠哉は少しだけ驚きながらも、いつもと同じような返事をした。
すると、急に真っ赤になった宮内が、慌てて言葉を付け加える。
「ジングルベルの方の聖夜ですっ!」
「ふふふ…言い訳みたいで可愛い」
「いっ、いいい、言い訳じゃなくてホントに…!」
「誠哉でいいよ。その代わり、僕も賢人って呼ぼうかな?」
「そんなのっ…」
「言ったでしょ?恋人を始めるの」
言葉と同時に、柔らかな感触が、宮内の頬にさらなる熱を与えた。
「イヤ……?」
「……イヤ……じゃない…です…」
「あ、敬語もダメ。今から禁止ね?」
「うぇっ…」
また、少しだけ、二人の心の距離が近づいたような気がした。
これから何度、こういう「歩み寄り」を続ければ恋人になれるのか…と、宮内は鼓動の収まらないままにそんなことを考えていた。
静かに流れる月日は、いつの間にか暦を弥生まで捲っていた。
いつもとは違い、ピシッとしたスーツに身を包んだ誠哉は、一世一代の大仕事に向けて、自宅を飛び出す。
…仰げば尊し…我が師の恩…
…教えの庭にも…はやいくとせ…
それは、あっと言う間に訪れた充の卒業式だった。
保護者として椅子に座っていた誠哉は、必死に涙を堪えながら卒業証書を受け取る充を眺めながら、穏やかな微笑みを浮かべる。
そして…
誠哉の隣には、充の卒業を誰よりも待ちわびていた雅樹が座っていた。
チラ、と、お互いに見た瞬間に瞳が合う。
「…充のこと、宜しくお願いします」
「こちらこそ…」
たくさんの希望を胸に抱いた小鳥たちが、今、まさに羽ばたこうとしている。
それを止めようなどと、誠哉は少しも思わなかった。
好きなところに、好きなように飛び立てばいい……
その代わり、もう、親鳥の真似っこはしないからね……
■ ■ ■
季節は流れ、少し気の早い春の息吹があちこちに感じられるようになったころ、充は荷物をまとめ、泣きながら家を出ていった。
別れを惜しんでくれる充の優しさに、誠哉は困ったように笑い、見れば雅樹は寂しげな表情をしていた。
「はい!さっさと出発しちゃいなさい。雅樹さん、泣き虫は嫌いだってよ?」
「兄ちゃん…っ…俺、時々は帰ってきてもいいんだよね……?」
「もちろん。……とは言っても、毎月のように帰ってこられると困るけどね。」
誠哉は、もう一度、あの秋の日とは違う気持ちで、充の背中を押し出す。
「行ってらっしゃい」
その夜、桜の咲く季節には珍しい、数十年ぶりの大雪が都内で観測された。
翌朝、眩しい太陽を肌に感じながら、誠哉は職場である会社に向かって徒歩で通勤していた。
辺りを見渡せば、雪景色の中で、通学途中の子供達がわいわいと大はしゃぎしている。
そういえば、昔、よく充と雪合戦して遊んだっけ。
ふと、誠哉は「婿に出した」弟のことを考えていた。
……降り積もった雪の下には、いくつもの新芽が春を待ちわびている。
だから、
願わくば、
…美しい若草が萌える春の訪れとともに…
僕は、いつまでも、君の幸せを、祈っているから…。
………僕の可愛い恋人の自慢も、今年中には出来るかな…?
よし、今夜、充にそのことでメールを入れよう。
『充に会わせたい人がいるんだ。僕の大好きな人を紹介したいから』
さっきまでよりも軽快になった足を従え、誠哉は空を見上げた。
そこに広がっていたのは、雲一つない快晴だった。
今日はいいことでもあるかな…?
あ…
もしかして…
また、賢人が可愛いことでも言ってくれるのかなー…
…なんちゃってさ。
何も言わなくても、賢人は可愛いんだけどね。
…と、余計なことを色々と考えていた誠哉は、足下の雪に足を取られ、派手に転んだ。
「あたたたた…」
七転び八起き!
それだからこそ人生は幸せ満開!
そう自分に言い聞かせた24歳の春は、まだまだこれからだった。
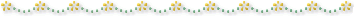
END
Material Thanks
...@FRONTIER(photo)...Little
Eden(lines)...
|