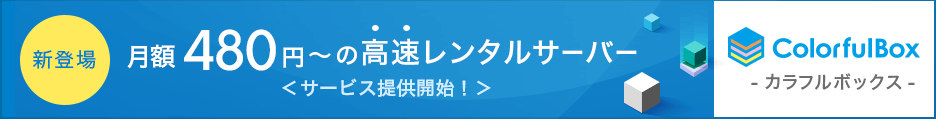
Crystals of snow story
*10年分のチョコレート*
2001バレンタイン企画
あれは10年前の冬。 眞一さんが僕をいたずらっ子から救い出してくれてから、数ヶ月後の事だった。 「ねぇ、2月14日ってなんの日だとおもう?」 幼稚舎の砂場で、僕は偉そうに研クンに聞いた。 その日、お弁当当番だった僕が、一個足らなかった牛乳をもらいに行ったとき、先生達が楽しそうに話していたのを聞いたんだ。 助けてもらってからずっと、素敵な素敵な眞一さんに、どうにか、幼いながらも、感謝と憧れの気持ちを伝えられないかと思っていた僕には、聞きかじったバレンタインデーって言うのは至極都合のいい行事だと思われたんだ。 「俺の誕生日でも、鈴ちゃんの誕生日でもないからわかんない」 研クンはたいして興味もなさそうに、水色のギンガムチェックのスモックを肘の上までまくり上げて、一生懸命光る泥団子造りに熱中していた。 ぬらした泥をボール状に丸め何日も乾かしては砂で磨くと、黒真珠みたいにぴかぴか光るから、当時僕たちの間ではこの玉を上手に作れる子は人気が高かったんだ。 僕は膝を抱えて、真側に跪くと、一列に並んだ研クンの宝物をつんつんと指で突っついた。 ほかの園児がさわると、すんごく怒るのに、どうしてか分かんないけど、僕だけには触らせてくれる。 「あのねぇ、バレンタイン・デーっていうんだよ。で、好きな人にチョコレートをあげたら、ホワイトデーって言うときに素敵なお返しがいっぱい貰えるんだって」 今思えば、先生達って、せこいこと考えてたのかもしれないけど、僕は耳にしたそれをそのまま鵜呑みにしてしまったんだ。 「チョコやったら、いいもんが貰えんのか?!」 それまで興味のなさそうだった研クンが、急に目をキラキラして聞き返した。 ほっぺに泥がちょっぴりこびり付いている。 「うん。好きな人にあげるとお返しにくれるんだって。 スモックのポッケからハンカチを取り出して、研クンのほっぺをごしごし拭ってあげた。 僕の方にほっぺを突きだして拭いてもらいながら、研クンはしばらく何かを考えているようだった。 「俺、いいや・・・・・・・・・」 「なんで??研クンもあげればいいじゃない?」 「だってよ。チョコをやったら、そいつが俺にまたなんかやらないといけないんだろ?俺、やっぱ、いいよ」 「ふ----ん」 研クンにそう言われて、何となく彼の言おうとする事は分かったけど、眞一さんが僕に素敵なものくれるんだと思ったら、僕はどうしても、その素敵な物が欲しくて、なんとしてでもチョコレートを渡さなきゃと思ったんだ。 |