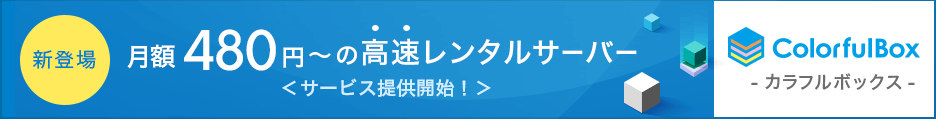
★もう一度だけ、ささやいて★
( 1 )
幾何学模様で彩られたモノクロームの球体。
たった一つのボールを二十二頭の若い獅子たちが奪い合いながら、ただひたすら追う。
走る、走る。
光り輝く若い汗を飛沫させながら、時にはぶつかり合い、罵声すら浴びせながら、ゴールをめがけてたった一つの球を打ち込むために。
いつしか、地面に映る獅子たちの分身が滑稽な程長い影に変わり、さっきまで燦々と降り注いでいた日の光が柔らかい色調に変わりだした頃、華奢な身体を木陰のベンチに隠していた一人の少年が立ち上がった。
独特の雰囲気を醸し出す少年は、ある種のカリスマすら感じさせる。
絹糸のような黒い髪、白磁の頬、潤んだ黒目がちな瞳。何より目を引くのが小さめでふっくらとした紅色の唇。
「みんなお疲れさま!」
ピィーと高く遠くまで響き渡る銀色のホイッスルを吹いて、鈴[すず]が練習時間の終わりを広いグランドで駆ける回る俺達に告げた。
広いコートの中を走り回って、くたくたにくたびれてぼろ雑巾のようになっている俺達と違い、フットワークの軽い鈴はすぐにグラウンドに隣接して建てられた、各運動部の部室が並び長屋のような形態をしたプレハブハウスの一室に戻り、冷蔵庫から用意して置いた冷たいお絞りを出してきて、みんなに一つずつ配り始めた。
「ハイ。研くん」
一番最後に、べったりと地面に両足を投げ出してぐったりと座り込んでいる俺の目の前に、鈴はひんやりとしたお絞りを差し出した。
「おう」
砂埃にまみれた俺の手にお絞りを手渡した鈴は、キョロキョロっと辺りを見回して、半径2~3メーター以内に誰もいないことを確かめると、やおら目を輝かして俺の側にしゃがみ込み、お約束の一言を待ちわびる。
俺は練習のせいで上がった息のまま、待ちわびる鈴の形のいい耳元に荒い息の残る口元を寄せて、
「はぁ・・鈴矢・・愛してるよ・・」
と囁いてやった。
当の鈴は瞼をギュッと閉じて俺の囁きを聞き、フルフルっと可愛らしく身震いをして、白磁の頬を紅く染めたまま、
「・ぁん・・」
細く白いのどの奥から、堪らないほど甘い声を出す。
「おら。今日の日課は終わったぜ!さっさと片づけちまって、来来軒のラーメン食いに行こうや!」
毎日のことなのに、鈴の漏らす喘ぎに似た甘い声を聞く度にドキリとする俺は、鈴の肩に手を置いておもむろにヨッコラショと立ち上がった。
俺に続いてあわてて立ち上がった鈴は、
「もう!せっかく僕が余韻に浸ってるっていうのに。研くん、ムード無いんだから」
グランドのど真ん中に立って両手を腰に置いたまま俺に文句を言い、ツンと顎を尖らせて、その可愛らしい鼻先をちょぴり顰めて見せた。
夕日に染まる、その顰めた顔すらも堪らなく可愛いから始末が悪い。
美少年って言う言葉はこいつの生まれるずっと前から有るんだろうけど、こいつがこの世に生まれてくる為にだけ用意された言葉なんじゃないかと思わせる程、鈴の風貌はただ整った顔立ちというだけではなく、どことなく危うく儚[はかな]げで、見目麗しい。
大人になっても鈴が凛々しい美青年になることはきっと無い。
鈴は永遠の『美少年』なんだ。
俺がそんなことを考えながら、冷たいお絞りで首筋の汗を砂埃と一緒に拭っていると、身軽な鈴はあちらこちらに白いスケルトンの洗濯籠を持って、みんなのお絞りを回収し始めていた。
「ありがとな、鈴ちゃん」
「鈴矢先輩!気持ちよかったス!」
「す、すいません」
口々に礼を言いながら、皆鈴に汚れたお絞りを返す。
マネージャーとは言え、全校生徒の崇拝の的である鈴から、毎日冷たいお絞りのサービスを受けられるとあって、新入部員の一年坊主なんかは、もうそれだけで舞あがっちまうんだから。
当の本人はあまり自分の事がよく分かっていないらしく、一人一人に、
「お疲れさま。今日は暑かったでしょう?部室に、冷たいレモネード作ってあるからのんでね」
なんて言いながら、それはそれは可愛らしく、天使のように微笑んでいる。
ここはエスカレータ式の私学の中等部で、俺と鈴は幼稚舎からずっと一緒の幼友達だ。
小学部までは共学なのだが中等部になると男女別々になる。
女子部は俺達が通っていた幼稚舎や小学部の同じ敷地内に短大まで有るのだが、男子はそこから電車で五駅ほど離れた場所に中等部、高等部が有り、大学は全く別の場所。
各学部によって至る所に点在しているマンモス校だ。
つまり、ここには十三歳から十八歳までの血の気の多い決起盛んなむさ苦しい男ばかりがいるってわけ。
そんな中に、触れなば堕ちん風情の、類い希なる美少年一人が混じっているのだから、全校生徒の崇拝の的になっても当然と言えば至極当然なんだが。
しかし、触れなば堕ちん風情と言うのはあくまでも見てくれだけのことで、こいつは結構一途で、幼稚舎の頃からずっと一人の人だけを頑なに思い続けているんだ。
それは俺!
と言いたいところだが・・・・・・・・
悲しいかな俺と同じ声を持つ俺の兄貴に鈴はずっと想いを寄せている。