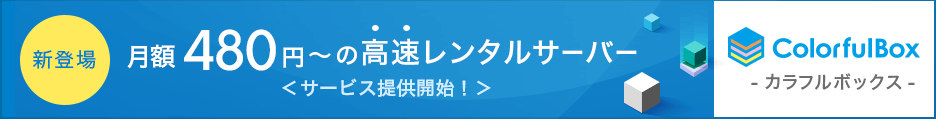
★もう一度だけ、ささやいて★
( 10 )
葉月さん、俺の誕生日なんか憶えてくれてたんだ。
鈴以外の人と過ごす初めての誕生日。
去年までは鈴も俺もお互いの誕生日には必ず一緒に過ごした。
小さな頃はお誕生日会を家でして貰っていたけど、ここ何年かは鈴と二人で食事に行って小さなケーキを二人で食べた。
柔らかな蝋燭の灯る誕生日やクリスマスだけ、鈴が俺の本当の恋人になったようで、毎年このつぎも鈴と一緒に過ごせますようにとケーキの上に立てた小さな灯火に俺は願いを込めていたのに。
葉月さんは帰り道にあるアウトレットショップでわざわざバイクを止め、何も要らないと断る俺の言葉に全く耳を貸さずに、カラージーンズを一本買ってくれた。
「研二。右手かしてみろ」
ショップの駐車場でメットを被りかけた俺に葉月さんは声を掛けた。
「右手?」
素直に出した俺の右手の薬指に今の店で買ったのだろう、葉月さんのポケットからさりげなく取り出された燻銀の指輪が填められる。
「右手の薬指は『恋人が居ます』って意味なんだそうだ。
鈴ちゃんを焦らすためだけにだれかを口説かなくても、これくらいならいいだろう?」「でも・・誰に貰ったって聞かれたらどうするんです?」
生まれて初めて填めた指輪はヒンヤリと冷たく、思ったより重く感じられた。
「俺じゃ役不足か?」
「とんでもない!だけど葉月さんの名前だしていいんすか?」
「光栄だね。研二は知らないだろうけど、おまえってさ、高等部でもかなり人気高いんだよ」
そう言いながらにっこり微笑むと葉月さんは黒いフルフェイスのメットをしっかりと被った。
ちゃっかり家の前まで送って貰った俺はバイクを降り、借りていたメットを返しながらプレゼントのお礼を改めて言い、ペコリと頭を下げた。気にするなと片手を挙げメットから僅かに見える目元だけで葉月さんは返事を返した。
俺は家の門の前に立ったまま葉月さんが爆音を轟かし、RX1000の巨体を巧みに操って走り去るのをうっとりとした憧れの眼差しで見送った。
はぁ・・・最初から最後まで何をしてもカッコイイ。
俺もいつかあんな風に成れたらいいな。
影も形も見えなくなってしまってもなお、買って貰ったジーンズの袋を胸に抱いたまま、俺はぼんやりと門の前に佇んでいた。
ほぉ~と溜息を吐いて、山茶花の生け垣にぐるりと囲まれた小さなアルミ製の門に手を掛けると、とっくに花の咲き終わった大きなツツジの木の茂みがガサと小さく鳴った。
暗闇に目を凝らすと春に咲くはずの花は、もちろん咲いてはいないのに葉陰に白い物がちらほらと見える。
「誰だ?!」
さっきまでヘッドライトの明るい光に晒されて閉じていた虹彩が急速に闇に馴染んで開いていくと、白い人影が見覚えのあるシルエットへと変化を遂げていく。
「鈴ぅ?・・・お前、何してるんだ?」
俺の問いかけに応えることもなく、鈴はツツジの根本で猫のように小さく背を丸めて膝を抱えていた。
「何をしてるって訊いてんだよ!」
俺の苛立った声にキッと顔を上げた鈴は、もの凄い形相で俺を睨み付けた。
「ほっといてよ!さっさと僕のことなんかほっといて家に入ればいいじゃないか!」
「ほっとけねえだろう。こんな夜中に何してんだよ」
「研くんこそ、そんな夜中まで葉月さんとなにしてたのさ!」
「鈴・・・?」
普段大人しい鈴の、もの凄い剣幕に押された俺はおずおずと鈴に右手を伸ばした。
「指輪まで・・貰ったんだ・・」
鈴は驚愕の面もちで俺の薬指を凝視した。
鈴の言葉に、ハッ!とした俺は慌てて伸ばした手を引っ込め胸元に引き寄せる。
「こ、これは・・・ち、違うんだ鈴」
なさけねぇ・・。俺なんでいちいち鈴に言い訳しなくちゃいけねぇんだよ!
「そっちの袋は何?服?パンツ?僕からのプレゼントは受け取れなくても葉月さんからなら指輪だって貰えちゃうんだね。
僕が去年指輪を贈ろうとしたら、研くんなんて言った?『そんなちゃらちゃらしたもんつけれるか』って僕のこと怒鳴りつけたじゃないか!」俺は怒りに燃える鈴の瞳から目をそらし、
「お前からは、指輪なんて貰いたくなかったんだ」
と、呟くと、鈍く光る銀の指輪に目を遣った。
そう、少女趣味と言われても指輪なんてのは好きだと告白した相手に送ったり送られたりするもんだと俺は信じてたんだ。
単に金持ちのお前が誕生日だからって買ってくれるもんなんかじゃねぇだろう。
一瞬身体を強張らせた鈴がふらりと立ち上がったとたん、さっきまでの激しい怒りが嘘のように消えていた。
「僕は随分長い間なにか大きく勘違いしてたみたいだね。
僕は研くんが僕のこと・・・・・・・・・
もういいや・・・・・・・・ごめんね。
僕の顔なんか、見たく無かったんだったよね。
そんなに前から・・・去年の誕生日よりも前から嫌われてたなんて全然気が付かなかったから・・・・・・・・・・・
研くんも酷いよ・・・葉月さんが好きなら好きって言ってくれればいいのに。
今にして思えばそうだったよね。
僕をサッカー部に誘ったのも葉月さんに言われたからだったし、毎日僕に『愛してる』って言ってくれてたのも元はといえば葉月さんとの約束があったからなんだものね。
僕は今日まで研くんがただ単に先輩として葉月さんに憧れてただけだと思ってたんだから・・・・・・・バカみたい」なんで、なんで、そんなこと、今更俺に言うんだよ・・・・・・
暗闇の中でふふふと笑った鈴のほの白い顔は凄く悲しそうだった。
「俺が葉月さんを好きだとして、それが鈴になんの関係があるんだ?俺達は恋人同士じゃない。お前は俺のことなんか何とも、親友とすら思ちゃいないくせに。
お前は兄貴が好きなんだろう?そのくせ兄貴に気持ちを伝える勇気がないから、お前に惚れきってる俺を兄貴の代用品にしてただけじゃないか!」「話そらさないでよ!そうだよ!僕は眞一さんが大好きだよ。ずっと、ずっと前からね。そんなこと、研くんだって、ずっと昔から知ってるじゃないか!」
そうさ、そんなことは今更、言われなくても分かっている。だけど、はっきりと宣言した鈴の声が俺の胸に鋭い痛みをもたらした。